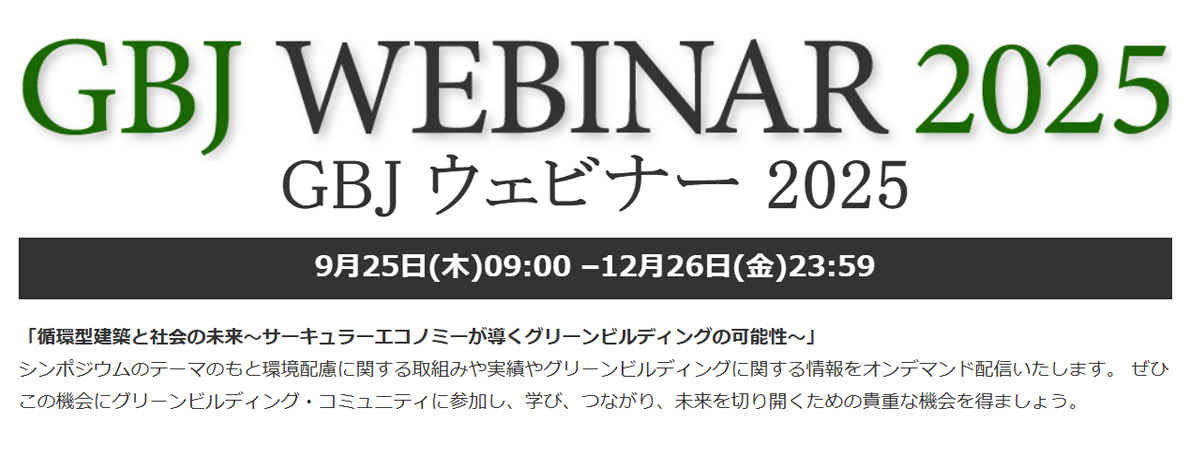プロジェクト概要
プロジェクト名:SMART INNOVATION ECOSYSTEM NOVARE
都市:東京
認証システム: LEED BD+C LEED v4
認証取得日:2024年1月16日
認証レベル:プラチナ
インタビューを受けた人:清水建設株式会社 小林 様
インタビューした人:GBJ運営委員 幸田淳貴

グリーンビルディングジャパン 幸田淳貴(以下、幸田):
施設の概要を教えてください。
清水建設株式会社 小林(以下、小林):
温故創新の森NOVARE は清水建設が事業構造・人財・技術のイノベーションを目的とし整備したものです。今回のLEEDプラチナを取得したNOVARE Hubは、NOVAREの幹にあたり、全体の建物を繋ぐ中央にあります。
幸田:
先ほどは館内を見学させて頂きありがとうございます。
その中で、注目したい所がありまして、超個別空調のところです。苦労した点など教えて頂けますでしょうか?
小林:
ピクセルフローとよぶシステムを今回開発しました。床面に600mmピッチでファンを入れています。利用者の一人一人の位置情報を活用して、暑いと感じる人では、ファンの回転量を増やして風量を増やし、寒い方には風量を減らし、個人の好みに合わせた環境を作り出す事で、全体としてエネルギー量も減るという考え方でやっています。
ファン自体はPC用のファンを活用しています。 PC用のファンを活用する事で低コストでの導入が可能なのですが、一方で数が多すぎて、一般的な空調制御システムでは制御出来ず、音楽ライブや舞台の照明を制御するシステムを採用して制御しています。
幸田:
もう一点、ノーアドレスというシステムを採用しているとの事で教えて頂けますでしょうか?
小林:
アクティブベースドワーキングという、誰でも好きな所で仕事して集中して仕事が出来るという考え方が最近一般的になってきた考え方かと思います。それに加えて私達はノーアドレスオフィスという考え方を採用しております。家具やテーブル、植栽、ホワイトボードなどすべての什器にキャスターが付いており、例えば、プロジェクトが始まった時は、少人数で島を作り、人数が増えていけば什器も増えていく、そんな環境の中で自分で好きな場所を選んで働ける環境を整えています。

幸田:
実際のLEED取得について教えてください。取得しようとした経緯を教えて頂けますでしょうか?
小林:
清水建設の様々な企業のお客様がLEEDに関心があり、社内にLEED取得をサポートするチームも居る事から本物件にてLEEDを取得しようとする事は初期の段階から決めておりました。
幸田:
清水建設様の東北支店などもLEED取得されておるかと思います。清水建設の中でLEEDのノウハウの蓄積など清水建設様のLEEDについてコメント頂けますでしょうか?
小林:
計画ごとに要求基準や地域性もあり、お客様ごとに検討するのですが、経験をもとに、LEEDのポイント確保に向けて、様々なノウハウが蓄積されています。
幸田:
ありがとうございます。先ほどのLEEDの中について、関心があるお客様が増えているのでしょうか?
小林:
はい。そう思います。例えば、国際的な企業ではLEED取得を前提に入居案件を探していたり、年次リポートでLEED取得案件での入居率を公表している場合もあります。
幸田:
ありがとうございます。LEEDの取得の際に、コンサルティング会社と協働されるパターンが多いかと思います。本物件について教えて頂けますでしょうか?
小林:
今回は、ヴォンエルフをコンサルタントとしてLEED取得を行っております。
清水建設内部のLEEDコンサルチームも参加し、本物件では協働しながら、ある意味ダブルキャストで互いの専門性を持ち寄り実務に当たりました。
幸田:
関係者が増える事で大変さもあったのでは無いでしょうか?
小林:
そのような事はなく、お互いの専門性、共通の認識がある事がむしろスムーズに申請実務に当たる事ができました。
ある項目があっても、お互いのチームで別の経験があるので、お互いに意見を出し合い良い関係性の中で業務に当たる事が出来ました。
幸田:
日本では、CASBEEという日本で開発された建物認証がよく使われております。
LEEDとCASBEEとの比較の中での難しさなど、そのあたりはいかがでしょうか?
小林:
LEEDの基準の内容が日本の基準とどう合致しているのか、読み解く事が必要です。例えばですが、日本は非常に水が豊富にありますが、世界では違います。LEEDの基準、日本の基準の違いをすり合わせしないといけない、CASBEEは日本で開発された認証ですので、そのようなすり合わせが必要無い事が大きいです。
また、一例ですがLEEDでは材料の運搬などで距離の基準があります。日本では南北に距離が長い国土ですが、鉄道やトラック輸送が非常に発達しており、距離が長くても効率的に材料を運搬する事が出来ますが、LEEDでは評価されません。日本の地域性などについても認めて頂けると良いなと感じます。
幸田:
その中で、LEEDの為に検討されたポイントとして、出入口の足拭きマットについて教えて頂けますでしょうか?
小林:
LEEDでは、室内への汚染物の持ち込みを制限する為に、出入口に足拭きマットを規定の長さ以上の設置を求めています。
しかし、当物件に限らず、東京ではほとんどの道路が舗装され、足元が汚い状態、泥等が付いた状態などで室内に入ってくる事はほとんどありません。
LEEDのポイント確保の為に、規定の足拭きマットの設置を検討しましたが、設計をする中で、オフィスエントランスとしての使い勝手や清掃性を検討し、もあり、他の項目でポイントを取ろうと決断しました。
幸田:
もう一つ教えてください。建材についても難しさがありましたか?
小林:
設計段階でLEED対象の建材を計画しても、コロナ禍で手に入らない事がありました。また、建材の認証が取れていると思って計画したが、実際はスペック上で満たしているだけで、認証は取れていないなどもありました。
幸田:
建材メーカーから、より認証材料があると良いでしょうか?
小林:
むしろ日本の基準の材料でLEEDとして認めて頂けると良いと感じます。
グローバルで展開されている建材メーカー様であれば、今後LEEDの発展と共に多少高い値段でも提供してくれると思いますが、日本のローカルの企業さんであれば、なかなか難しいと思います。基準を緩めて欲しいと言う訳ではありませんが、ローカルの企業さんの製品も日本の基準のJISなどはクリアしている訳ですから、そういう製品も認めていただける方法があると良いと感じます。
幸田:
最後の質問になります。環境認証というものがもっと社会に広がっていくには、何が必要だと思いますでしょうか?
小林:
所有したり利用したりする、お客様が、環境認証を取得した事で、優位性が獲得出来る、アピールする事が出来る。そうすれば、おのずと取得に向けて広がっていくと思います。
幸田:
ありがとうございます。インタビューは以上となります。

英語版はこちら
Click here for English version