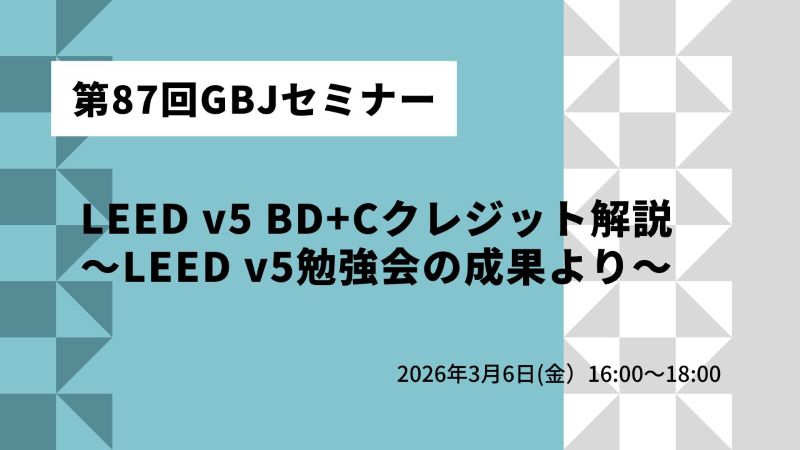プロジェクト概要
プロジェクト名;シックスセンシズ 京都[Six Senses Kyoto]
都市:京都
建物用途:ホテル 全81室 延床面積 11,169.61㎡
認証システム:LEED v4 BD+C:Hospitality
認証取得日:2024年7月7日
認証レベル:シルバー
インタビューを受けた人:
小坂 幹 Motoki Kosaka[リシェス・マネジメント株式会社 執行役員・開発事業本部デザイン・エンジニアリング部長]
山﨑 康弘 Yasuhiro Yamazaki[リシェス・マネジメント株式会社 開発事業本部デザイン・エンジニアリング部]
新實 功平 Kohei Niimi[シックスセンシズ 京都 セールス&マーケティング部]
インタビューした人:
宮崎淳 Atsushi Miyazaki[GBJ コンテンツWG]
@ Six Senses Kyoto

宮崎:
Six Senses Kyotoのコンセプトを教えていただけますでしょうか。
山﨑:
Six Sensesは「サステナビリティとウェルネス、非日常の体験」をコンセプトに、1995年に設立されたホテルブランドで、世界21か国に26件のホテルがあります(2025年8月現在)。
Six Senses Kyotoは日本初のSix Sensesとして2024年4月にオープンしました。もともとこの場所にあったホテルを建て替えるにあたり、突出したコンセプトを持つ特徴的なホテルにしたいという考えから、Six Sensesというホテルブランドを選択しました。
新實:
Six Senses Kyotoは、そのSix Sensesのサステナビリティとウェルネスを重視したコンセプトに基づいて設計され、運営されています。蓮華王院(三十三間堂)に近く、豊国神社に隣接しているという閑静な東山区にあり、古くからの伝統や文化と最新のテクノロジーを融合したホテルとなっています。
宮崎:
Six Senses Kyotoで、サステナビリティとウェルネスのために行っている、具体的なサービスとしてはどのようなものがありますか?
新實:
ウェルネスのコンセプトを体現するため、ロビーを含むインテリアは自然素材で作られ、緑豊かな中庭に向かって開いており、Six Senses Kyoto独自の香りが感じられる空間となっています。部屋に置かれるアメニティにも環境に配慮した製品を採用しており、歯ブラシは竹製、歯磨き粉もチューブレスのものを採用しています。部屋のミネラルウォーターもペットボトルではなく、ガラス瓶に地下のラボで瓶詰めしたものをお届けしており、容器を再利用することと輸送をなくすことで、CO2 排出を減らすことに貢献しています。また、豊国神社との間にはホテル専用の無農薬菜園があり、専任のスタッフが野菜やハーブなどを栽培しており、レストランやスパで使われています。キッチンから出る廃棄物は堆肥化され、その畑でも使われています。また、宿泊されているお客様がその畑で体験学習をすることもできるようになっています。そのほかにも、サステナビリティとウェルネスをテーマとした、様々な体験型プログラムが用意されています。

宮崎:
Six Senses Kyotoは、宿泊者としてどのような方々をターゲットとされていますでしょうか?
山﨑:
「サステナビリティとウェルネス」をコンセプトにしているホテルであることから、海外の日頃から「サステナビリティ」を重視しながら生活をされている方々にご宿泊いただき、滞在中に様々な「ウェルネス」な体験をしていただきたいと考えています。また、宿泊客だけでなく「サステナビリティ」に興味のある地元の方々にも、施設を利用していただきたいと考えています。宿泊は海外の方のご利用がほとんどですが、レストランやスパなどは地元の方にも多くご利用いただいています。
宮崎:
そもそも、どのような目的で、LEED認証を取得しようと考えられたのでしょうか?
山﨑:
Six Sensesブランドのホテルは、全てのLEED認証を取得することがルールとなっており、ホテルブランドが決定した時点でLEED認証を取得することは決まっていたと言えます。当ホテルではLEED ver.4でシルバー認証を取得しました。Six Sensesブランドの他のホテルとしては、サウジアラビアとインドのホテルでLEEDプラチナ認証を取得しており、ローマのホテルではLEEDゴールド認証を取得しています。日本では、Six Sensesブランドにおいて、初めてLEED ver.4での認証を取得したホテルということになります。
宮崎:
LEED認証を取得するうえで、苦労されたことはどのようなことですか?
山﨑:
最も苦労したことは、シャワーの心地よさと節水機能の両立でした。節水性能が高いシャワーヘッドだと、どうしてもシャワーを浴びた時の心地よさが低くなってしまう傾向にあります。Six Sensesが求める高い性能と、LEED上必要になる節水性能を両立させるため、数多くの製品を実際に試してみたうえで、慎重に採用するシャワーヘッドを決定しました。開業して一年が経ちますが、シャワーの水量についてのクレームは一度もありません。

宮崎:
LEED認証を取得してよかったことはありますか?
新實:
最近、インタビューや取材を受ける際に、環境についての認証を取得しているかどうかを聞かれることが増えてきていると感じています。環境やサステナビリティに配慮していることを表明するホテルが増えてきている中で、なかなか差別化が図れなくなってきており、自ら表明しているだけではなく第三者認証を取得している、ということが重要視されるようになってきているのだと思います。定性的な議論になりがちな環境やサステナビリティの評価について、実証性を重視する傾向にある、ということはとても良いことだと考えています。今後ますます、環境配慮やサステナビリティについての、実績を求められることが増えていくと考えていますので、LEED認証を取得しているということは、重要な武器になっていくのだと考えています。
山﨑:
少し前から、倉庫業の分野でもLEED認証の取得が増えてきていました。認証を取得している倉庫だとテナントの入居が早く決まるので、投資家さんとしてもそのような物件に投資をしたいという傾向が明確にあり、ホテルにおいても今後このような認証の取得が注目されていくことになると考えています。投資家の方にとっても、LEED認証の取得は注目される項目になってきていると感じています。
小坂:
LEED認証取得の際に行ったコミッショニングの結果も、今後運用を行っていくうえでの重要なデータだと思っています。このデータに基づき最適な運用を行っていくため、ホテルサイドでタスクフォースを立ち上げ、検討を行っています。

宮崎:
LEEDのプラークが、アースラボに展示されていましたが、LEED認証ホテルであることをプロモーション等で活用されていますか?
山﨑:
Six Sensesは、まだ、「サステナビリティ」という言葉が一般的でなかったころから、環境やサステナビリティに配慮したホテル、ということを表明しているブランドであり、LEED認証を取得したことだけではなく、様々な環境に対する配慮を行っており、そのようなホテルの先駆者であるという自負があります。LEED認証そのものを前面に押し出してのプロモーションは行っておりませんが、今後も、環境への配慮をはじめとしたサステナビリティの意識を大切にしながら、さまざまな取り組みを続けていきたいと考えております。
宮崎:
その他に、Six Senses Kyotoならではの、取組みはありますでしょうか。
小坂:
Six Sensesの要望で、風水コンサルを登用し、建物全体の形状や家具の配置等を風水の視点からもチェックしています。風水は、抽象的な自然の大きな流れのようものから、長い時間をかけて規則性を見いだしてきたものであり、そのような視点と現代の定量的な評価の両方を採用しているところが、Six Senses Kyotoの特長だと言えると思います。京都の町は、もともと風水に基づいて作られたといわれており、その重要なカギとなるのが鞍馬山です。そのため、ロビーには鞍馬山から着想を得たアートを飾っています。

宮崎:
Six Sensesは、全てLEED認証を取得するのがルールであるとお聞きしましたが、今後、新たにSix Sensesブランドのホテルを建設される計画はありますでしょうか。
小坂:
現在、国内で2つのSix Sensesのホテルを計画していますが、どちらもLEED認証を取得する予定です。ホテル用途の建物はエネルギー使用量が多く、よい点数を取得するのが難しい傾向がありますが、Six Senses Kyotoで認証を取得した経験を活かして、対応していこうと思っています。また、LEEDの同じバージョンで認証を取得することで、Six Sensesにおける環境的取り組みの進化を、客観的に評価する手法としても使えるのではないかと考えています。
宮崎:
Six Senses Kyotoにおけるサステナビリティやウェルネスの様々な取り組みについていろいろなお話を伺い、感心させられると同時に、Six Sensesの長年にわたる先駆的な取り組みにとても感銘を受けました。また、全てのSix SensesのホテルでLEED認証取得をしようとしていることの必然性についても、よく理解することができました。
本日は、インタビューにご対応いただき、ありがとうございました。
英語版はこちら
Click here for English version