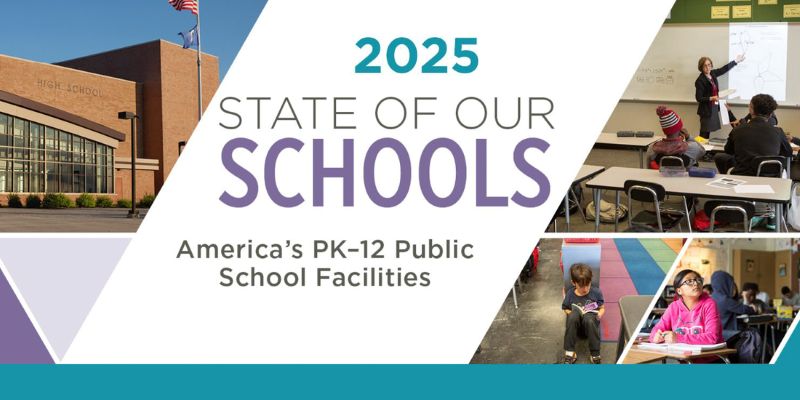ウェルビーイングを中心に据えた都市生活の設計は夢ではなく、“選択”である。
現在の都市は、気候変動による混乱をはじめとして、複数の課題に次々と直面している。しかし、こうした複雑な状況の中にこそ、驚くほど大きな可能性が存在している。都市は、単なる経済活動の拠点やイノベーションの中心地に留まらず、人間の健康、公平性、レジリエンスの原動力にもなり得る。
これは、私が最近参加したディスカッション「ウェルビーイングの為のデザイン:全ての人にとってより健康的な都市づくり」の中心テーマでもあった。このイベントは、イタリア外務省によるイタリア館(2025年大阪・関西万博)と、シンガポール政府観光局によるシンガポール館(〃)が共同で主催し、両国の国交樹立60周年を記念して開催された。
この場はまさに、「どうすれば、より人間らしく、より包括的で、より再生力のある都市をつくれるのか?」という問いを投げかけるのにふさわしい場であった。
デザインは常に人々の行動や体験を形作ってきた。今、変わってきているのは、健康とウェルビーイングを大規模に優先するために、どれほど意図的にデザインを使っているかという点だ。健康をインフラや公共空間、行政に組み込んでいる都市は、生活の質を向上させるだけでなく、長期的なレジリエンスも構築している。
WELLスタンダードのような科学的根拠に基づくフレームワークは、大局的な公衆衛生の目標を、現実の生活改善へと変換する柔軟なツールである。これにより、地方自治体や組織は、ウェルビーイングを空間と政策に組み込み、その進捗を測定することが可能となる。実際に多くの都市が市庁舎などの公共施設でWELL認証を取得することで模範を示し、先導的な役割を果たしている。
近年では、メンタルヘルス、社会的孤立、労働の公平性、緊急時対応といったテーマへも注目が高まっている。こうした課題に真摯に向き合い、デザインと政策で対応する都市こそが、将来の危機に耐え、市民をより強靭に支えることができる。
心強いのは、これらの考え方が実際に広がりつつあることだ。しかも、それは大都市圏だけでなく、小規模な地域や伝統的でない空間にも浸透している。芸術ホール、交通ハブ、生物親和性や文化的アイデンティティを重視する職場空間など、さまざまな場所で、ウェルビーイングが「後付け」ではなく「設計の前提」として認識され始めている。
結局のところ、都市の強さは、そこに住む人々をどれだけ支えられるかにかかっている。
私たちは、経済や制度だけでなく、個人やコミュニティの為にも機能する都市を設計するためのツール、知識、そして推進力を有している。
そして、今私たちに問われているのは、その設計を、意図的に行うかどうか。
なぜなら、人々の為に都市を設計することでこそ、都市はその本来の力を発揮できるからだ。
IWBI記事 原文(2025年7月22日)
https://resources.wellcertified.com/articles/the-power-of-a-city/