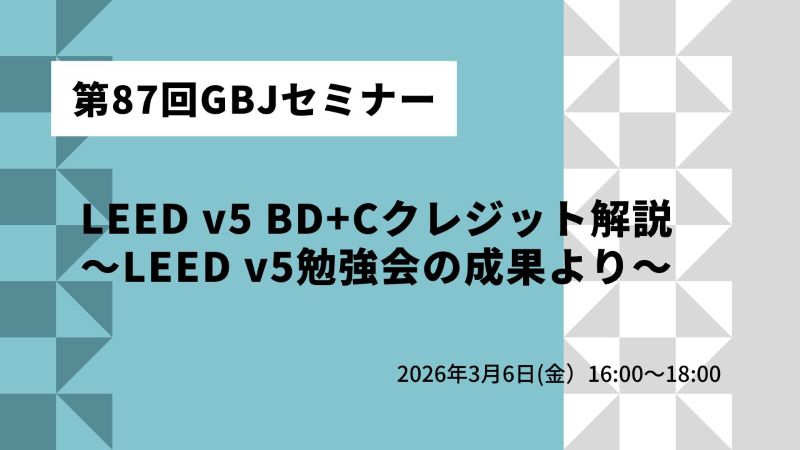プロジェクト概要
プロジェクト名:Aquila
都市:埼玉
認証システム:LEED v4 BD+C:Core and Shell
認証取得日:2024年9月3日
認証レベル:標準認証
インタビューを受けた人:レンドリース・ジャパン株式会社 宮本順子
インタビューした人:GBJ理事 橋本誠
昨年9月に認証を取得された、AquilaのLEED認証について、レンドリース・ジャパンの宮本順子さん(建設部シニア・プロジェクト・マネージャー)にお話しを伺いました。

グリーンビルディングジャパン 橋本誠(以下、橋本):
なぜデータセンターのプロジェクトでLEED認証の取得を目指したのでしょうか。
レンドリース・ジャパン株式会社 宮本順子(以下、宮本):
レンドリースでは、サステナビリティ・フレームワークと目標を策定し、自社のアセットで様々な取り組みを行っています。特に環境面においては、「ミッション・ゼロ」を宣言し、独自のロードマップに基づき、2025年までにScope1、2に起因するCO2排出をカーボンニュートラルとし、2040年までにはScope1、2および3に起因するCO2排出を完全にゼロとすることにコミットしています。
具体的なアクションとして、当社が世界各国で開発するプロジェクトでは、数あるグリーンビル認証の中でも、世界的なスタンダートとなっているLEED認証の取得は欠かせないものとなっています。日本のプロジェクトにおいても、LEED認証の取得が必須となっています。
橋本:
LEED認証の取得を目指して特に苦労した点は何でしょうか。
宮本:
今回のプロジェクトでは内装部分はテナント工事であったためBD+CのC&Sを選択しました。テナントとの工事区分の取り決めによりC&Sの工事範囲は限定的で、ほぼスケルトンの状態でテナントへ引き渡しを行いました。そのため、選択できるクレジットの範囲も限られており、「如何に得点を獲得するか」が大きな課題でした。
「エネルギー削減率の最適化」についての評価項目については、スケルトンの場合、外皮の断熱性能を上げることが当社でできる主な対応でした。当初は、この対策だけでは、Prerequisiteを満たすことも危ぶまれたため、テナントへ当社の取り組みを説明し、ご理解いただき、テナントが設置する高効率のチラーをエネルギー削減計算に含めることで、エネルギー削減の要件を満たす道筋をつけることができました。
当社と同じく、積極的に環境面に配慮した経営を行っているテナントを誘致し、協力し合える体制を整えることも重要だと考えます。
橋本:
スコアカードで高ポイントなカテゴリーなど、取組みとして特徴的なことがあれば教えてください。
宮本:
Location and TransportationとWater Efficiencyカテゴリーでの得点が高かったです。Water Efficiencyの取り組みを例として挙げると、集水面となる屋根が広いため、降る雨の回収量が多くなることが期待できました。そのため、雨水を再利用するためのシステムを導入し、イノベーションのカテゴリーでは満点を取得しました。
LEED認証取得という取り組みをプロジェクトで推進するためには、その取り組みをプロジェクト内で広く共有し、関係者の協力を得ることが不可欠です。それまでLEED認証取得に携わったことがなかったプロジェクトのチームメンバーや施工関係者の方々が、「これはLEEDポイントに貢献できるかな?」という会話をしているのを耳にしたり、サステナビリティについて関係者へ情報発信したりする姿を目にする機会が増えていき、グリーンビルディングやLEED認証への認識がプロジェクト全体に広がっていくのを感じました。このような、何気ない会話から、認証取得の課題解決につながるヒントが得られることもあると思います。
橋本:
データセンターとしてグリーンビルディングに取り組むことの意義についてのお考えがあれば教えてください。
宮本:
データセンターはエネルギー使用量が特に多く、グリーンビルとは真逆の立場にいると考えられています。エネルギーを使うのはサーバーだと思われがちですが実は空調です。24時間365日稼働するサーバーの熱を冷やすために冷房の負荷が高くなります。そのため、寒冷地にデータセンターを建設したり、海底データセンターの検証等も行われています。
一方、ネットワークの肝である「速さ」を求めるために、都市型のデータセンターの需要が高いことは変わらずで、熱負荷の地球的課題、コスト的問題は、その負担を軽減することが、デベロッパー含め業界全体の喫緊の課題となっています。
CO2を大量排出する立場だからこそ、社会的責任を果たす上でグリーンなデータセンターを目指す意義があります。「何をしたら少しでもCO2排出を削減できるのか?」を関係者全員で検討するのが大切で、まさにLEEDを活用し、Integrative Processを実施し、実行しています。
英語版はこちら
Click here for English version